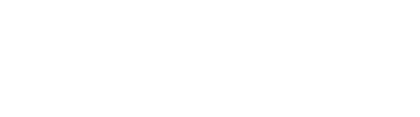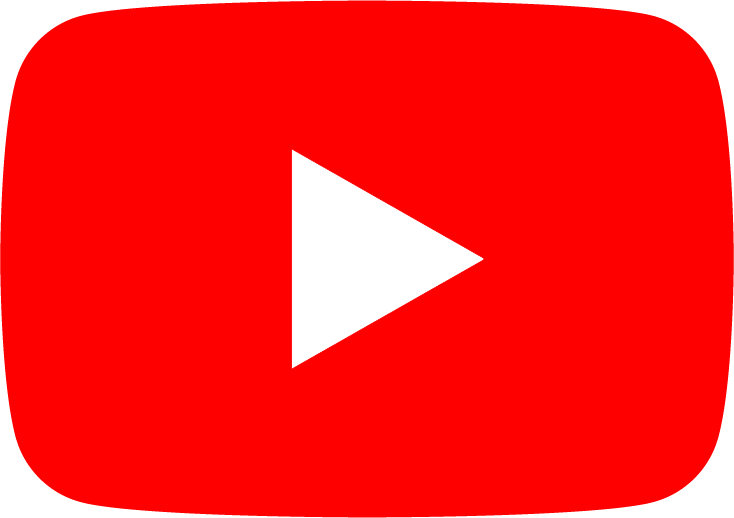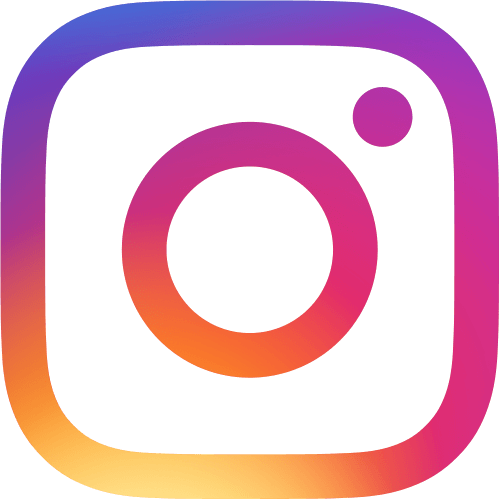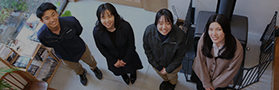重陽の節句の魅力:菊の香りと不老長寿を願う特別な日
日本の伝統的な行事である「五節句」をご存知ですか?人日の節句(1月7日)、上巳の節句(3月3日)、端午の節句(5月5日)、七夕の節句(7月7日)、そして最後にくるのが重陽の節句です。あまり知られていないかもしれませんが、この節句には古来からの願いと、秋ならではの美しい風習が詰まっています。
重陽の節句とは?
重陽の節句は、旧暦の9月9日に行われる行事です。日付が奇数の中で最も大きな数字である「9」が重なることから、「重陽」と呼ばれています。昔の中国では奇数は縁起の良い「陽」の数とされており、その「陽」が重なる9月9日は、さらにめでたい日と考えられました。
この日には、不老長寿や無病息災を願う様々な風習があります。特に主役となるのは、秋を代表する花である菊です。
菊にまつわる風習
重陽の節句は別名「菊の節句」とも呼ばれ、菊を愛でる風習が中心となります。
- 菊酒(きくざけ): 菊を浮かべたお酒を飲む風習です。菊には邪気を払い、寿命を延ばす力があると信じられていました。菊の香りが漂うお酒は、見た目にも美しく、心も体も清めてくれるようです。
- 菊の着せ綿(きせわた): 前夜に菊の花に綿をかぶせ、朝露を含んだその綿で体を拭うという雅な風習です。これもまた、不老長寿を願う意味が込められています。
- 菊合わせ(きくあわせ): 様々な種類の菊を持ち寄り、その美しさを競い合う行事です。平安時代から貴族の間で行われ、菊を愛でる文化が発展しました。
なぜ重陽の節句は知られていないの?
現代では、ひな祭りやこどもの日、七夕に比べて重陽の節句が一般的に知られていないのはなぜでしょうか?これは明治時代に新暦が採用されたことが大きく関係しています。旧暦の9月9日は、新暦では10月中旬から下旬にあたります。本来、菊が見頃を迎える時期と合っていた行事も、新暦の9月9日ではまだ菊が咲いていないことが多く、季節感がずれてしまったためです。
今、重陽の節句を楽しむには?
せっかくの美しい風習ですから、現代でも楽しむことができます。 旬の食材である栗や秋ナスを使った料理を味わったり、栗ご飯を炊くのも良いですね。また、お花屋さんで菊の花を飾り、香りを楽しむのもおすすめです。心静かに秋の訪れを感じ、健康を願う時間を持ってみてはいかがでしょうか?
古くから伝わる菊の香りに癒されながら、今年の重陽の節句を特別な日にしてみましょう。
ヤマヒロ新築事業部企画設計課築山大祐
____________________
姫路市・加古川市・たつの市を中心に
兵庫県播磨地域で木の家を建てたい方
新築・リノベ・リフォームをご検討の方必見!
____________________
!!!最新情報が届く!!!
\ヤマヒロ公式アカウントをお友達追加/

!!!販売&見学予約受付中!!!
\区画割から考えたヤマヒロ流分譲住宅/

!!!平屋の事例も見れる!!!
\カタログや資料を取り寄せてみる/