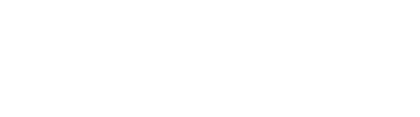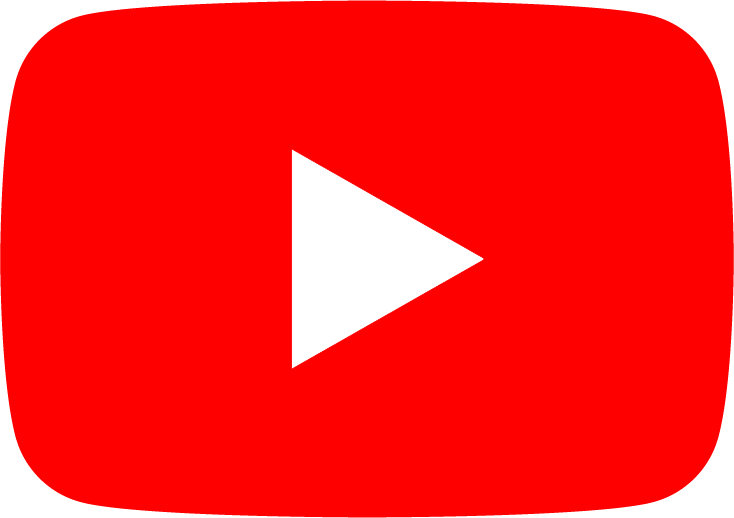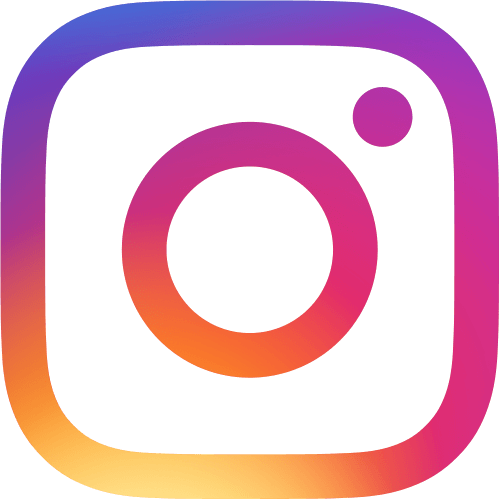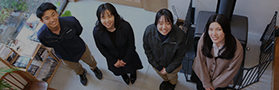お盆に多くの人が里帰りをするのは、ご先祖様を敬い、家族や親戚と集まって供養をするという、日本の古くからの文化や風習が深く関わっています。
その始まりには、日本の土着信仰と仏教の教えが融合した物語が関係しています。
仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」の物語
お盆の正式名称は「盂蘭盆会」といい、仏教の物語に由来します。
昔々、お釈迦様の弟子の中に、非常に優れた神通力(超能力)を持つ「目連(もくれん)尊者」という人がいました。目連尊者は、亡くなった母親がどうしているか神通力で見てみたところ、なんと餓鬼道に落ちて逆さ吊りの苦しみを受けていることを知りました。
餓鬼道とは、生前に強欲であったり、食べ物を粗末にしたりした人が落ちるとされる世界で、常に飢えと渇きに苦しむ場所です。目連尊者は、母親の苦しむ姿を見て悲しみ、お釈迦様にどうすれば母親を救えるか相談しました。
お釈迦様は目連尊者に、夏の修行を終えたばかりの多くの僧侶たちに、たくさんの食べ物を施し供養をするようにと教えました。目連尊者がその教えに従って供養を行ったところ、その功徳によって母親は苦しみから解放され、極楽へと導かれました。
この物語が日本に伝わり、ご先祖様を供養する仏教行事として「盂蘭盆会」が定着しました。そして、この「盂蘭盆会」の教えが、日本の古来の祖霊信仰(亡くなった人は山の神様となり、時々家に帰ってくるという考え方)と結びつき、現代のお盆の形へと発展していきました。
江戸時代の「藪入り(やぶいり)」
また、お盆に里帰りをする風習には、江戸時代の「藪入り」という習慣も関係しています。
当時は、住み込みで働く奉公人や、嫁に行った女性は、普段はなかなか実家に帰ることができませんでした。しかし、お正月とお盆の時期だけは、実家に帰ることが許されていました。この貴重な休息と帰省の機会が「藪入り」と呼ばれ、時代とともに形を変え、現代のお盆休みへと受け継がれてきたとされています。
これらの歴史と文化が融合し、お盆は「ご先祖様の霊が家に帰ってくる時期」とされ、家族や親戚が集まってご先祖様を迎え、供養をする大切な行事として定着しました。そのため、多くの人がこの時期に実家へ里帰りをするようになったのです。
ヤマヒロ新築事業部企画設計課 築山大祐
____________________
姫路市・加古川市・たつの市を中心に
兵庫県播磨地域で木の家を建てたい方
新築・リノベ・リフォームをご検討の方必見!
____________________
!!!最新情報が届く!!!
\ヤマヒロ公式アカウントをお友達追加/

!!!販売&見学予約受付中!!!
\区画割から考えたヤマヒロ流分譲住宅/

!!!平屋の事例も見れる!!!
\カタログや資料を取り寄せてみる/

!!!町屋 x アーケード!!!
\町屋リノベーションプロジェクト/